
さて、食道具 庖丁の展示会と研ぎセミナー 研ごう会vol.2。
いよいよのメインイベント、庖丁研ぎセミナーの開始!
先生は、南丹市八木で庖丁調整士というお仕事をなさっている廣瀬康二氏。
食道具 竹上, 庖丁 竹上 庖丁コーディネータ 食道具 廣瀬康二
短く刈り上げた頭に、はっきりとした目鼻立ち、きりり!とした雰囲気。
昨今のソフトな男性を見慣れている目には眩しかったわ!
例えるなら…そう、三島由紀夫のような。
一目見たら忘れられないインパクト。
※好き放題いってます。ごめんなさい。

2日間に渡り、午前の部・午後の部それぞれ5〜6人ずつかな?
少人数制でじっくりと教えていただきました。
私の参加した会は、主婦の方、若いお嬢さん、そして本職の若い板前さんたち。
ちなみに私は木綿キモノに割烹着で参加。
なんか思いっきしオカンやったわ(^^;;
みんなそれぞれの庖丁を、事前に研ぎたい庖丁をお預けして、
それを一本一本廣瀬さんが診断して(それぞれの特徴や、様子を詳しいメモにされてました)
研ぐ前の調整(ひずみをなおしたり、形を整えたり、一定の厚みにしたり)までをして下さってました。
我が家は奮発して購入したものの、
手入れに自信がなくてイマイチ使いこなせていない出刃包丁をお願いしていました。
みなさん、両刃のステンレスの庖丁から料理人さんの片刃の本格的な庖丁まで
さまざまな庖丁を持ってこられていたので、
それぞれの特徴にあった研ぎ方を教えていただくことに。
そして、ただどうやって研ぐか、という技術だけでなく
庖丁とつきあっていく心構えまで、丁寧に教えて下さったのです。
続きを読む前に…♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!
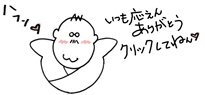
![]()
![]()
よく「庖丁の管理」と言う言い方をするけれど、
「管理」というのは、こちらの都合で相手を自分の意志に従わせること。
庖丁は、「日々の『守り(もり)』をしてください」と。
「守り」とは、自分の心をそえてお世話すること、手入れをすること。
庖丁は、きちんと正しく研がれることによって、
食材の抵抗をなくしてスッと切れるようになり、
また切れ味の良さが長持ちするようになるそうです。
では、そのようにして切った食材は何が違うのか?
まず、見た目が違う。
断面のツヤも違う。
エッジの食感が違う。
繊維をつぶしていないので、鮮度を保ち、
旨味を流さず、火が入りやすく、味も入りやすい。
ああ、私の拙い文章では、お話の万分の一も伝えられないので、
ぜひ廣瀬康二さんのブログをご覧ください!
食にまつわる、興味深いお話てんこもりです!
さて、実践!

先生が研ぐと、動きの一つ一つが綺麗で、
音もスピーディで軽やか。

でも、いざ自分でやってみると、
角度に気をつけると、ストロークの長さがおろそかになり、
ストロークに気をつけると、手をそえる場所がおろそかになり…
ああ、もう何をやってるのか分からない!!
幸い食いしん坊オットがきっちり動画を撮影してくれたので、じっくりゆっくりおさらいしなくちゃ!
具体的な庖丁の「守り」の仕方は、
とても私の伝えきれる所ではないので、ここでは詳細を書くのは遠慮します(;_;)
私の割烹着姿だけではなんなので、
ご一緒した、準ミス着物さんの美しい着物姿を。
彼女とは以前、別のイベントでもご一緒させていただいたのですが、
お顔を隠してしまうのがもったいないほどの別嬪さんです♪

とてもリズミカルに手際良く、研いでらっしゃいました♪
廣瀬先生、そしてこの素晴らしいイベントを企画して下さったshop&gallery yds(ショップ&ギャラリー ワイディーエス)のみなさま、
本当にどうもありがとうございました!
ランキングに参加しています♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!
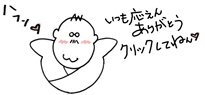
![]()
![]()
あー行きたかったなぁ。
料理をするなら、包丁ぐらい研ぎたいんやけど、いつも同居人にやってもらいっぱなしで。
あいにくこの日は用事があって、ほんま残念でした。
>ぽんさん お返事遅くなってごめんなさい!今年もよろしくお願いします。今年こそ、ぜひ神戸で呑みましょう♪ ダンナさん、研いでくれるんだ!いいな〜。そうそう包丁、毎回すごく好評なんだって。きっと来年もあるよー!それまでに私も練習しとかなくっちゃ。