
着物タテヨコ会でお邪魔した、
日本古来の植物染で有名な、染司よしおかさんの工房のおハナシ、続き。
※染司よしおかさんでは、通常見学を受け付けてはいらっしゃいません。
今回は縁の深い着物タテヨコ会として、特別にお邪魔させていただきました。
紫と紅については前回のおハナシで。
その続きをこってりと。
さて、赤い色には本当に様々なバリエーションがあってビックリ!

これは茜(あかね)。
黄色みを含んだ赤、
「茜色」というと、夕焼け空を思い出すわ。
「赤い根=あかね」という由来で、
染めるのには赤い根っこを用います。
日本の茜の根っこは細くて、
中国やインドの茜の根っこは太いのだそう。

茜を見せていただきました。
ハート形の小さな葉っぱの、可憐な植物。
この植物の根っこから、あんな鮮やかな色がとれるだなんて!
昔の人はどうして気がついたのかしら。
そして、

蘇芳(すおう)。
暗く濃厚な赤で染められた絹糸は、艶やかで本当に美しい…!
すでに奈良時代には珍重されていて、
正倉院に納められた宝物にも用いられているそう。
でも、用いられる蘇芳の樹木(樹木の芯に色素がある)は日本では育たなくて、
当時もインドやマレー半島などから輸入されていたのだとか。
「蘇芳」で検索するとたくさん出てくる、鮮やかなフューシャピンクの花を咲かせる「花蘇芳」とは
別物なのね。
続きを読む前に…♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!
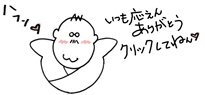
![]()
![]()
続いて、

カイガラムシ…(-” -)
ちょっと青みを含んだ、暗い赤。臙脂(えんじ)。
えー、虫とかムリムリムリ…
調べようと思って検索かけたら、大量の虫画像出てきて、もうムリムリムリ…orz
全世界に分布しているらしい、多種多様なカイガラムシの仲間たちの中で
インドや東南アジアに生息しているカイガラムシの仲間からとれるのだそう。
ちなみにメキシコやペルーのカイガラムシの仲間からとれる色素も
「コチニール」「ケルメス」などと呼ばれて、古くから珍重されています。
すごい油分を含んでいて、
塗料や食品のコーティングにも使われるのだそう。

コレは虫本体ではなくって(本体だったら触れないよ!!!)
「樹脂様の虫体被覆物質」というもの。固い。
そして、臙脂の最初の画像で写っている、丸いもの、

これは臙脂綿と呼ばれる、色素を含ませた丸い綿で、
中国から輸入されたもの。
なんかこのまま飾っておきたいような趣きがあるわ。
でもカイガラムシの色…orz
またもやこってり書いてしまった…。
メモを見ながら、あれこれ調べながら、
知らないことを知るのは楽しいことなので
ついつい夢中になってしまうわ。
続く。
※染司よしおかさんの作品は、染司よしおか京都店でご覧いただけます。
また、工房の製作を追ったドキュメンタリー映画「紫」が、
10/20より渋谷イメージフォーラムにて上映されます。
大阪では2013年に上映予定だそうです。
吉岡幸雄、福田伝士の情熱を追ったドキュメンタリー映画「紫」
〜色に魅了された男の夢〜
ランキングに参加しています♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!
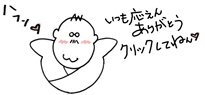
![]()
![]()

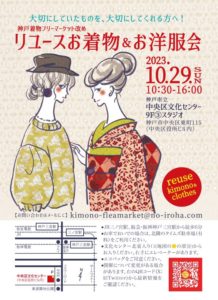






コメント