
着物タテヨコ会でお邪魔した、
日本古来の植物染で有名な、染司よしおかさんの工房のおハナシ、続き。
※染司よしおかさんでは、通常見学を受け付けてはいらっしゃいません。
今回は縁の深い着物タテヨコ会として、特別にお邪魔させていただきました。
さて、赤に負けず劣らず、様々なバリエーションがある黄色。

これは山梔子(くちなし)。
先に紹介した紅を用いて染める、東大寺二月堂のお水取りのための椿で、椿の芯の黄色を染めるのがこの山梔子。
ちょっと赤を含んだ、はっきりとした明るい黄色。
プリーツを寄せた、オブジェのようなユニークな形の果実からとれる黄色は、
食品や先の紫と同様に漢方薬にも用いられてきたのだそう。

黄蘗(黄膚、黄柏とも。きはだ)は、ちょっと青を含んだ?レモンイエローのような
これも明るい黄色。
黄蘗の樹木の皮を剥いだもので、
陀羅尼助などといった生薬に古くから用いられてきた生薬。防虫効果もあるのだとか。

工房の庭を案内していただいた時にもあった黄蘗。

一度皮を剥ぐと、皮は再生しないのだそう…。
皮がない、と言うのは樹木にどんな影響があるのかしら。
そういえば中学生のとき、教科書で志村ふくみさんの桜で染める話を読んだ。
桜で染める時は花びらではなく、蕾が芽吹いた枝、
これからまさに咲かんとする枝を使うとあった。
当然ながら、煮て染料に使ってしまえば桜は咲けない訳で、
命で染める、その重みを語ってらしたように記憶している…あまりにも雑な説明で申し訳ない。
続きを読む前に…♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!
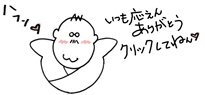
![]()
![]()
さて続いて、

刈安(かりやす)。
ちょっと黒を含んだような鄙びた黄色。
刈安はイネ科の、すすきのような植物の葉から染めます。
この刈安は傾斜の強い斜面を好むので、
古くから滋賀の伊吹山で生産されていたのだそう。
工房でも伊吹山の刈安を使っているそうですが、

お庭にも、ちょろりと刈安、ひょろりと細い葉っぱ。
乾燥させると当然茶色になるのだけれど、
この青い葉っぱを見ていても黄色は連想できないわ。
色って染料単体で染まる訳でなく、
媒染と言う行程があるのだけれど(媒染についてきちんと説明できるほどの知識はアリマセン。ググってね。)
よしおかさんの工房では、媒染に用いられているのも
鉄・植物の灰・ミョウバンなど、全て天然の原料なのだそう。

これはミョウバンの結晶。
大きな岩塩のよう。
そうそうこのミョウバン、消臭効果があるから
スティックタイプのデオドラントにもなってる。私も使ってるわ。
大半の染料はミョウバンで発色するのだけれど、
中には鉄で媒染する色もあり、その場合は黒くなるのだそう。
本当に色を染めるって不思議。
今回、これもとても不思議だったのが、
緑を染める天然染料がないと言うお話。
自然の世界には、あんなにたくさんの緑の色があるのに?

この美しい緑の色は、
藍と黄色を重ねることで染めてあるのだそう。
どちらの色を先に染めるのか、
どんな色を重ねるのかで、多種多様な緑が染め上がります。
そしてハナシはまだまだ続きます…。
※染司よしおかさんの作品は、染司よしおか京都店でご覧いただけます。
また、工房の製作を追ったドキュメンタリー映画「紫」が、
10/20より渋谷イメージフォーラムにて上映されます。
大阪では2013年に上映予定だそうです。
吉岡幸雄、福田伝士の情熱を追ったドキュメンタリー映画「紫」
〜色に魅了された男の夢〜
ランキングに参加しています♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!
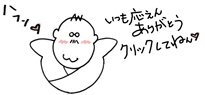
![]()
![]()

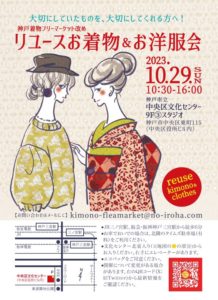






コメント